適切な意思決定支援に係る指針(アドバンス・ケア・プランニング)
(令和7年4月23日制定)
1.基本方針
山梨大学医学部附属病院では、すべての患者がその価値観に沿った最善の医療・ケアを受けられるようにする。多職種で構成された医療チームが患者や家族等に適切に説明を行い、十分に話し合いを重ねることで、患者本人の意向や価値観を尊重した医療・ケアを提供するよう努める。ただし、生命予後を短縮することを目的とした積極的安楽死は本指針の対象外とする。
2.人生の最終段階における医療・ケアについて
人生の最終段階における医療・ケアでは、患者が意思表示を行うことが難しくなり、意思が十分に尊重されないまま医療行為等が決定される場合がある。当院では、厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に基づき、意思決定支援に至るプロセス(図1)を適切に踏み、患者本人の意思決定を支援し、その価値観に基づいた医療・ケアを行うことを原則とする。
治療やケアは、医学的な妥当性や適切性を慎重に判断し、患者や家族等に十分に説明を行ったうえで、ともに最善の方針を考える。どのような決定においても、患者の痛みや苦痛をできる限り緩和し、心や社会的な問題にも対応できるよう医療・ケアチーム全体で努力する。
3.医療・ケアの具体的な決定プロセス
1)病状・治療・今後の見通しについての説明
①希望の確認
・患者や家族等に対し、説明を希望する内容(病状・治療・今後の見通し)を確認する。
②説明の実施
・主治医を含む医療チームで、患者や家族等にわかりやすく病状や治療内容を説明する。
・今後の見通しについても、希望がある場合は可能な範囲で説明する。
③不確実性への対応
・治療経過が予定通り進まない場合を想定し、柔軟な対応が必要であることを患者や家族等に説明する。
④価値観の尊重
・変化が生じた場合、患者・家族の価値観を尊重して計画を調整する。
⑤代理意思決定者の指定
・意思表示ができなくなる事態に備え、患者の意向で代理意思決定者を指定する場合は、その意思を確認する。
・指定された代理意思決定者の情報をカルテに記載する。
2)本人の意思が確認できるとき
①患者の意思確認
・患者の意思を直接確認する。
②医療・ケア方針の協議
・家族等や医療・ケアチームと協力し、患者の意思を基本に方針を決定する。
③継続的支援
・患者の意思が変化しうることを前提に、常に意思を表明できる環境を整える。
④話し合いの継続
・必要に応じて、繰り返し家族等と医療・ケアチームで話し合う。
⑤記録と共有
・話し合いや決定内容をその都度、カルテに記録し、医療・ケアチーム内で共有する。
3)本人の意思が確認できないとき
①推定意思の確認
・家族等が患者の意思を推定できる場合、その内容を聞き取る。
②方針の決定
・推定された意思や患者の価値観をもとに、医療・ケアチームと方針を検討・決定する。
③推定困難な場合の対応
・推定が難しい場合は、過去の発言や行動から価値観を参考に、十分に話し合いを行い、慎重に方針を決める。
④意見不一致への対応
・意見がまとまらない場合は、専門家(臨床倫理コンサルテーションチーム等)を交えた話し合いを実施し、助言を受けながら、合意形成に努める。
⑤記録と共有
・話し合いの内容と決定事項をカルテに記録し、医療・ケアチームで共有する。
4)認知症等で意思決定が困難な場合
①状態の確認
・認知症等による意思決定能力を確認する。
②ガイドラインの参照
・厚生労働省「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン」を参照する。
③価値観・意思の尊重
・過去の言動や生活歴から患者の意思や価値観をくみ取り、尊重する。
④話し合いの実施
・家族等および医療・ケアチームで、患者の立場に立った方針を慎重に話し合う。
⑤決定と記録
・方針決定後、その内容をカルテに記録し、共有する。
5)身寄りがない患者の場合
①身寄りの有無と判断能力の確認
・患者に身寄りがあるか、意思決定能力があるかを確認する。
②行政支援の依頼
・必要に応じて、福祉事務所などの行政機関に支援を依頼する。
③意思の尊重
・本人の意思が把握できる場合は、それを最大限尊重する。
④ガイドラインの活用
・判断が困難な場合には、厚生労働省「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」を参照して方針を検討する。
⑤記録と共有
・決定内容をカルテに記録し、関係者と情報を共有する。
4.人生の最終段階の定義について
人生の最終段階には、はっきりとした定義はないが、一般的には以下のような状況を指す。
- 医師によって回復の見込みがないと診断され、数週間から数か月のうちに死亡が予期される場合
- がん末期のように予後が数日から2~3か月と予測ができる場合
- 慢性疾患の急性増悪を繰り返し、予後不良に陥る場合
- 神経難病、脳血管疾患の後遺症や老衰など、数か月から数年をかけて死を迎える場合
人生の最終段階かどうかの判断は、患者の状態を踏まえ、多職種で構成された医療・ケアチームの適切かつ妥当な判断によるべき事柄である。緊急時には、生命の尊重を基本として、医師が医学的妥当性と適切性を基に判断するよりほかないが、その後、多職種で構成された医療・ケアチームによって改めて検討する。また、その判断を家族に伝える際には、看護師等が同席し慎重に行う必要がある。
人生の最終段階における医療の開始、不開始、中止等のあり方は、患者や家族の人生観、宗教、社会的背景によって異なる。そのため、一人ひとりの患者の背景を踏まえ、患者にとって最も適切な治療やケアを提供するには、医療・ケアチームの協力が必要である。患者や家族が判断に悩む場合には、その意向を大切にしながら、医療・ケアチームと共に話し合い、慎重に方針を決定する。
5.人生の最終段階における医療・ケアの具体的な方針
1)医療・ケアの開始、不開始、中止等について
①患者・家族等の価値観の把握
・患者および家族等の背景・価値観・意向を丁寧に聞き取る。
②医療・ケアチームによる多角的な検討
・医学的妥当性、適切性を多職種チームで評価。
・医療・ケアの開始・不開始・中止の可能性を整理する。
③話し合いの実施
・チームと患者・家族等で繰り返し話し合いを行い、方針の検討を進める。
④方針の決定
・患者・家族等の価値観と医学的判断をもとに、方針を最終決定する。
⑤記録と共有
・決定した方針は、ACPに関する意思表示に、話し合いの経過はカルテインフォームドコンセント欄に記載し、関係者で共有する。
2) 患者や家族等への説明と対応
①医師による説明
・医師が中心となり、患者の状態や治療方針について家族へ十分に説明する。
②看護師等の同席と支援
・看護師等が同席し、患者・家族の不安や疑問に寄り添って対応する。
③話し合いの継続
・意見がまとまらない、または判断が困難な場合は、医療・ケアチーム内で慎重に検討し、繰り返し話し合う。
④第三者の助言
・必要に応じて、倫理コンサルテーションチームや第三者の専門家集団からの助言を受ける。
⑤最善の方針の模索
・患者にとって最善の方針を目指して、再度、患者や家族等と、話し合いと説明を行う。
⑥記録と共有
・説明内容と合意の経過は、その都度、カルテに記録し、医療・ケアチームで共有する。
3)宗教的・社会的背景の尊重
①背景の確認
・患者や家族の宗教的信条、文化的背景、人生観などを確認する。
②内容の理解と尊重
・医療・ケアチーム内で共有し、その背景や価値観を十分に理解する。
③方針への反映
・宗教的儀式、死生観、治療の希望等に応じた柔軟な対応を計画に反映する。
④柔軟な対応の実施
・多様な価値観を尊重した医療・ケアを実践する。
⑤記録と継続的配慮
・背景と対応内容をカルテに記録し、継続的に配慮できるようにする。
4)長期的な視点での対応
①疾患の特性を理解
・慢性疾患や老衰といった経過をとる患者の全体像を把握する。
②ケアの長期計画立案
・急性増悪時のみでなく、長期的な医療・ケアの方針を立てる。
③患者の尊厳を重視
・最期まで患者の尊厳が守られるような支援内容を検討・実施する。
④チームでの継続的支援
・医療・ケアチームで情報を共有し、定期的な見直しを行う。
⑤家族等との連携
・家族等と連携を図りながら、患者の望む過ごし方を支援する。
⑥記録と見直し
・ケア計画と対応内容をカルテに記録し、必要に応じて更新する。
参考資料
- 厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(2015)https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000197665.html
- 厚生労働省「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212395.html
- 厚生労働省「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」(2018)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/miyorinonaihitohenotaiou.html

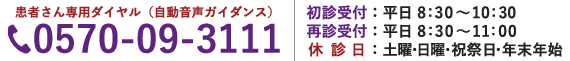


 初診の方
初診の方
 再診の方
再診の方
 救急の方
救急の方
 入院・お見舞いの方
入院・お見舞いの方
 医療関係者の方
医療関係者の方